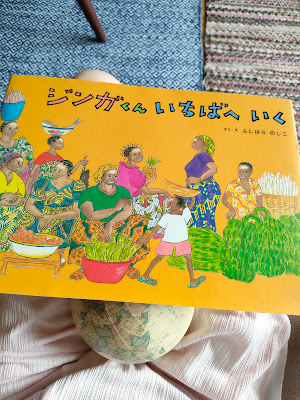「水車小屋のネネ」の表紙はもう一つある。
2枚とも中嶋香織さんの装幀だ。
500ページ近い物語の中に中嶋香織さんの挿絵が入っていて、登場人物がほのぼのと薄らぼんやりと描かれていて、この物語の世界を邪魔することなくわたしに更なる温かみを与えてくれた。
著者は、津村記久子さん。
「毎日新聞」に2021年7月1日から2022年7月7日まで連載されたものを加筆修正されて出版された、と記されている。
主人公は18歳と8歳の姉妹。
とにかく、実母とその婚約者以外の登場人物の全員が良い人たちばかり。挿絵と共に、姉妹の周りには温かい空気が流れている。
わたしがなぜ、この本を知って読んでみようと思ったか。
わたしたち夫婦がキンシャサ暮らしの時に飼っていた、コンゴインコの”ヨウム”が出てくるからだ。ヨウムは、コンゴに野生の鳥として生息して、3歳児の知能を持つ賢鳥と言われ、寿命も70年、となんだか人間のような鳥なのだ。
とはいえ、夫のプロジェクトで働く技術者のムッシュが我が家に持ってきてくれたヨウムの「ぽんちゃん」は、なぜか一芸たりともしなかった。ただ鳴くだけ。男の人が鳥かごに近づくと、ギャーギャーとわめく始末だった。
藁(わら)の細い筒状のものに入れられて我が家にやってきて、さぞかし狭苦して辛かったことだろう。夫は、捕獲の時のトラウマが心に残っているのではないか、と心配していた。
体毛はグレー。尾羽のみ鮮やかな朱色だった。
その尾羽と同じ色のココヤシと、乾燥トウモロコシを好んで食べ、水を与えて、毎日、小屋に敷いている新聞紙を取り換えた。新聞紙をくちばしでつついて、めちゃくちゃにするのだ。びりびりに破いた新聞紙と糞とココヤシやトウモロコシの食べかすで、鳥小屋は派手に汚された。留まり木にいつも捕まっているので、夫が丈夫な木の枝を見つけてきて、小屋に2本の留まり木を渡して、行ったり来たりできるようにした。
夫が小屋の掃除をしようと手を入れたらものすごいわめき声を上げるので、わたしが掃除係だった。一度、わたしが餌を手のひらに置いて食べさせようとすると、指をかまれてしまい、アフリカでのことだったので、手のひらから食べ物を与えることはあきらめた。
キンシャサのアパートのお隣さんの日本人ドクターが音楽を聴かせると良いというので、ドクター宅のヨウム(”ルージュ”と言った)に音楽を流し始めたので、我が家のぽんちゃんにも音楽を聴かせた。たくさん話しかけた。でも、懐いてくれることはなかったように思う。夜には、籠に布切れを掛けて安らかに眠る状態にもした。
朝、布切れを取るのが遅いと、布切れをくちばしで突いてぼろんぼろんにした。
それでも、かわいいぽんちゃんだった。
(ぽんちゃん、というのは、わたしの息子が小さい頃の呼び名だった。)
大きくなった時、籠も大きなものに替えた。
「水車小屋のネネ」を読んでいて、なんてネネは賢いんだろうと感心したし、しっかり登場人物の主要な”人物”なのだ。それくらいに、皆に愛され溶け込んでいた。
わたしたちの愛情の掛け方が薄かったのかなあ~と反省もした。
そんなキンシャサでのぽんちゃんをネネと重ねながら読んだ。
久しぶりに、ああ、この物語がずっとずっと続いてほしい~と思いながら読んだ。
2人以外の皆が善人で、普通の市井の人たちで、飛びぬけて成功するわけでもなく、コロナの時期もたんたんと過ぎていく登場人物の普通の暮らしぶりが、本当に心に沁みわたる良い物語だったなあ。
2024年本屋大賞の2位になっている。
我が家のキンシャサのぽんちゃんは、その後、夫の運転手をしていた(その後、ある国の大使専属運転手になった温厚なムッシュだった。)現地の男性が引き取ってくれて、かれの家族の下で人生を終えたと連絡をもらった。ヨウムの平均寿命としてははるかに短い(我が家に来たのが2013年で、そのとき、ぽんちゃんが何歳だったのかは不明。コロナ時代より前に亡くなっている。)人生だったはずだ。